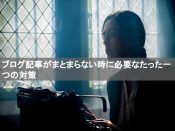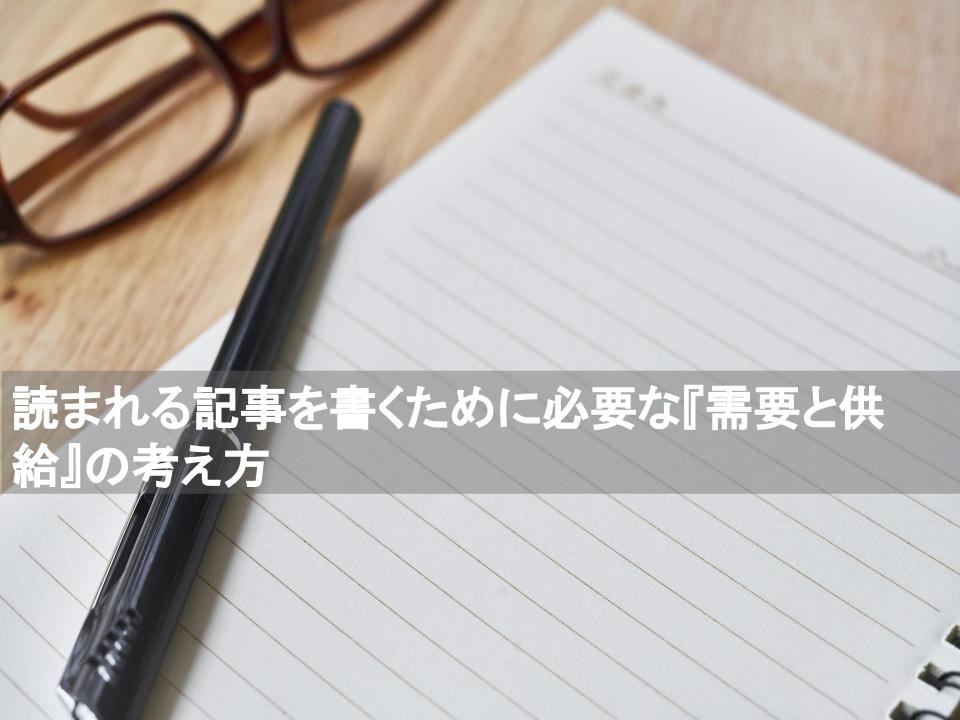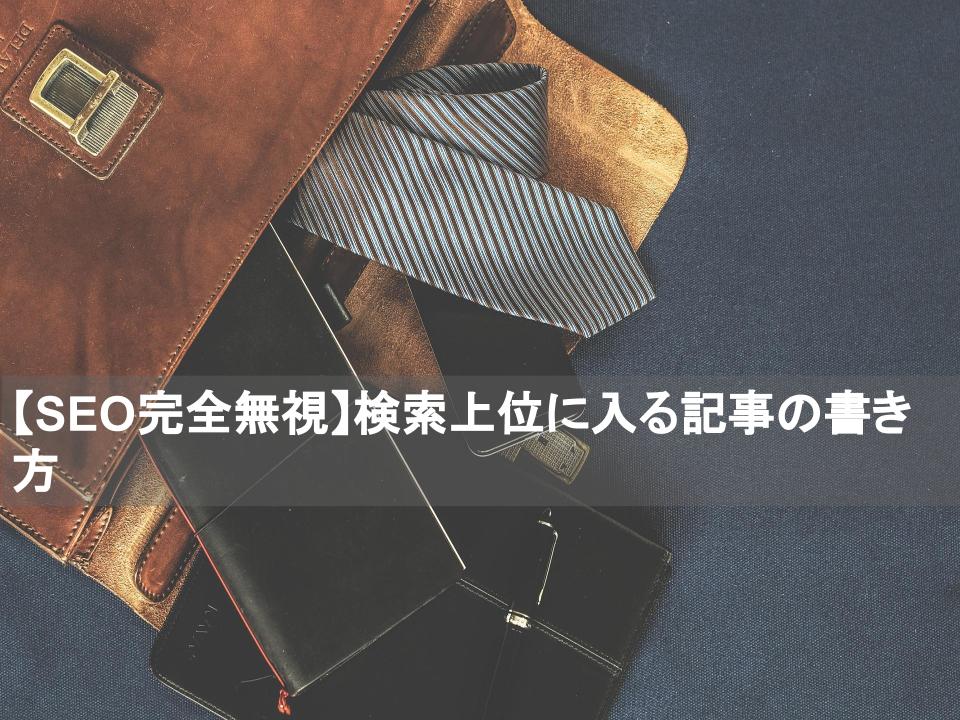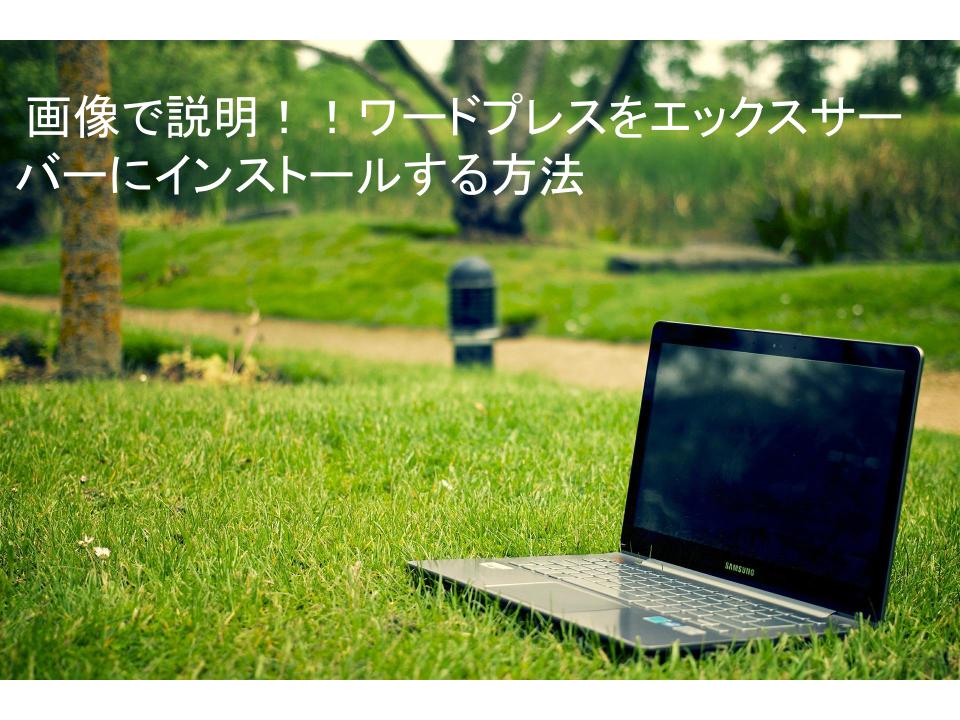※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
文章力がなくてもブログ記事が書けるようになる方法
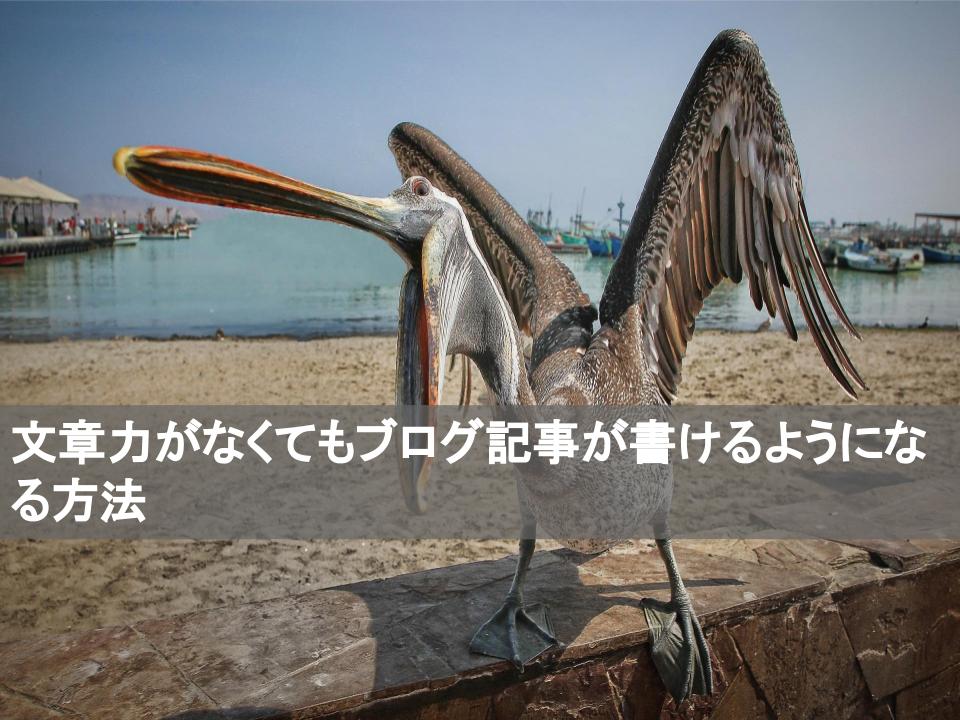
どうも!!『らしらん』(rasiran)です。
ブログを書き始めたはいいけれど、うまく文章がまとまらなかったり、文章を書いている途中で自分でも何を伝えたかったのか分からなくなってしまうなんてことはないでしょうか?
もともと私も文章を書くのが苦手で、当初は1記事書くのに2週間かかるような状態だったのですが、今回紹介する方法でまとまりのある記事が短時間で書けるようになりました。
私のような文章力の低い人間でも活用できる再現性の高い方法を紹介しようと思います。
目次
読みやすい文章を書きたければ『型』を使う
少し思い浮かべていただきたいのですが、長い間親しまれているアニメやテレビドラマには、ストーリーのパターン(型)が『パッと』思い浮かぶものが多いのではないでしょうか?
たとえば、アンパンマンや、名探偵コナン、水戸黄門なんかがそうだと思います。
ストーリーが単純にもかかわらず、なんだか引き込まれてしまいますよね?
材料の下ごしらえから時間をかけて作った『筑前煮』よりも、電子レンジでチンしただけの『冷凍のから揚げ』の方がおいしかったりするように、
ブログの文章も実はシンプルな『型』を意識した方が読みやすい文章が出来上がったりするものです。
それでは、どのような『型』を使えばいいのかをお伝えしようと思います。
ブログの文章構成の『型』に使われるパーツはメインの3つと、2つの補足だけ
読みやすいブログは以下のようなパーツで構成されます。
初めの3つが重要で、残りの2つは補足的に記事に『まとまり』を出すために使います。
- What(記事の中で何を伝えようとしているのか?結論)
- Why(なぜ、それを伝えようとしているのか?)
- How(具体例や、理由)
- 補足説明(誤解を生みそうな事や例外へのフォロー)
- What(という訳で、結論は○○ですの様に締めくくる)
少しわかりづらいですよね?
具体的に、文章を作って紹介してみましょう。
それでは何でも文章にできることを証明するために、パッと思いついた『お茶漬け』を題材に文章を作ってみたいと思います。
文章構成の『型』を使えば『お茶漬け』が題材でもブログ記事は書ける
- What
『お茶漬けに入っているアラレはいらない』 - Why
『お茶を吸って柔らかくなったご飯と、硬いアラレの歯触りのギャップが受け入れられない』 - How
『他にも歯触りの悪い例として、貝に砂が入っていた時のガリっとした感触っていやですよね?』 - 補足説明
『実を言うと、お茶をしっかりと吸ってふやけたアラレは嫌いじゃない。でもアラレにお茶を吸い込ませるには待たなければならない』 - What
『私は、ふやけたアラレは嫌いじゃないけれど、ふやけるまで待つ時間や、ガリっとする歯ざわりが嫌だから「お茶漬けに入っているアラレはいらない」と思うわけです。』
初めに選んだお茶漬けという題材がアレなので内容は微妙ですが文章の流れ的に、まとまったのではないでしょうか?
『型』を使うと毎回似たような記事になるのでは?という心配はいらない
勘のいい人は、『お茶漬け』を題材にした構成で気づいたかもしれませんが、『型』は使う人や場面によって、かなりの融通がききます。
先ほどの例を使うと、記事の中で何を伝えようとしているのか?のWhatのところで、『お茶漬けに入っているアラレはいらない』としましたが、
『お茶漬けにアラレが入っていると歯触りが悪くなる』のように先ほどは、Whyのパートに含めたところまでWhatのパートに含めてしまっても問題がないわけです。
これだと、同じように『型』を使っても違う文章が出来上がりますよね?
『型』のために文章を作るのではなく、文章を作りやすくするために使うのが『型』
忘れてはいけないのが、
- 目的: 簡単に文章をつくれるようになる
- 手段: 『型』を使う
ということです。
よく『型』についてお伝えすると、『型』を極めようとする人がいるのですが、全くの無駄です。
『型』を使う理由は、ブログ記事の『1つの章に入る内容』を限定することで、章に含まれる内容がシンプルになり、書き手は記事を書きやすく。
そして、記事の読者からすると内容が理解しやすくなるという訳です。
そこが達成できれば、『型』を極める必要はありません。
まとめ
今回は、ブログ記事をうまく書けるようになる為に、『型』を使う方法を紹介しました。
ブログ記事が書けなくなる多くの要因は、内容の詰め込みすぎです。
まずは、『型』にそった『シンプルな文章』を作って、それから『肉付け』を行うことで『具体性』のある分かりやすい文章が出来上がります。
最後までお読みいただきありがとうございます。